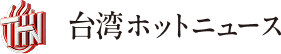「トランプ関税」が地政学的秩序を再構築している
4月2日、トランプ米大統領が「相互関税」を発表して以来、米国株式市場は数日間にわたり急落し、投資家からの信頼は大きく落ち込みました。関税率がウォール街の予想を大きく上回り、まさに「ブラックスワン(予測不可能な事態)」を目の当たりにしたからです。
特に10年物国債が売却され、利回りは4月3、4日に下落した後、4月7日から9日にかけて突然急上昇しました。
これによりトランプ氏は4月9日に劇的な転換を行い、中国に対する相互関税を125%に引き上げ、さらに薬物のフェンタニルが米国に流入している問題を取り上げて20%を加え、関税は145%に達しました。一方で他の国に対する相互関税は90日間延期され、交渉の時間が設けられました(すでに75カ国以上が米国に報復せず、交渉の準備をしている)。
トランプ氏の狙いは、唯一米国に報復した中国に対して関税を145%に引き上げることであり、他の国々の相互関税は交渉期間中、基準関税の10%に設定されています。
表面的にはトランプ氏は全世界に対して相互関税を課していますが、実際には中国を標的にしています。このような関税戦争は、貿易や経済の範疇を超え、強い地政学的な意図があることは明らかです。
関税とは伝統的に産業政策の手段であり、保護主義の道具でもあります。
たとえば、自国の自動車産業を保護したい場合、輸入自動車に関税を課します。
トランプ氏の「革新」は、関税をマクロ経済の手段に引き上げ、製品でなく国を対象に課税し、当該国との貿易による米国の赤字額と関連付けて税率を設定したことです。
関税は、自国産業の保護や貿易赤字への対処だけでなく、トランプ氏の運用ではさらに2つの経済的な目的が強調されています。
第一に、関税を利用して外国企業に米国への投資と工場設立を促すことです。
米国内で生産・販売すれば、関税を支払う必要がありません。
さらに言えば、トランプ氏の意図は、米国での雇用機会を創出し、「製造業の空洞化」の問題に対処し、米国の「再工業化」を推進することです。
第二に、関税収入を財政収入の新たな源と見なすことです。
以前の関税は特定産業の保護が主な目的でしたが、現在の関税はそれ自体が目的であり、この方法で財政収入を増加させ、連邦赤字を軽減し、財政均衡の原則の下で、関税収入を利用して他の分野で減税を推進することができます。
たとえば、所得税や営業税を引き下げることで、家庭の消費や企業の投資を促進し、実体経済に活力を与えることができます。
この一連の関税操作により、トランプ氏は関税を新たな高みに引き上げ、地政学的なツールとして同時に3つの目標を追求しています。
第一の目標は、「戦時経済体制」を構築し、戦争に備えることです。
米国の再工業化を推進する過程で、トランプ政権は重要産業の米国内での定着を強調しています。
重要産業には2つの大きなカテゴリがあります。
第一のカテゴリは「戦略物資産業」であり、鉄鋼、石油、半導体、医薬品、レアアース(希土類)、造船、自動車(自動車の生産ラインは戦争勃発後、軍需品や武器の製造に転用できる)などが含まれます。
グローバル化の時代において、米国は製造業を海外に移転または外注し、再び輸入するという国際分業戦略を採用してきました。
しかし、コロナ禍の期間中、米国は中国からマスクや医薬品を正常に取得できず、ロシアはウクライナ戦争を始めると半導体を入手できなくなり、一部の武器システムを生産できず、前線の消耗に対応できませんでした。
米国はこの「サプライチェーンの断裂」の問題を認識し、戦略物資産業を米国本土に引き戻す決意を固めました。
このような「サプライチェーンの安全性」は経済安全保障であり、国家安全保障の一部でもあります。
第二のカテゴリは「先端技術産業」であり、量子コンピューティング、スーパーコンピューター、低軌道衛星、ドローン、ロボット、シリコンフォトニクス、核融合などが含まれます。米国はこれらの先端技術を自ら掌握し、中国企業による盗用を防ぐことで、米国の優位性と覇権を効果的に維持する必要があります。
米国の立場から見ると、戦略物資産業と先端技術産業の両方が米国本土に定着する必要があります。
戦争が勃発してから輸入しようとしても間に合わないからです。率直に言えば、米国の再工業化自体が、戦時経済体制の構築を意図しています。
第二の地政学的目標は、中国の大国としての台頭を抑制し、米国の世界的リーダーシップを維持することです。
現在、トランプ氏の真の狙いが明らかになってきました。彼の関税政策は、間違いなく中国を標的にしたものです。
米国の地政学的戦略は、中国の台頭を根本から断ち切り、中国の経済力や技術力を削ぐことにあります。
そうすることで、中国共産党が国際舞台で米国に対抗し続ける力を奪い、挑発的な行動を取る余力を無くそうとしているのです。
輸出に高関税をかけることで、事実上これまで中国に与えていた米国市場を閉ざし、米中間の「貿易最恵国待遇」は完全に崩壊しました。
この結果、中国が過去30年間続けてきた「輸出主導型経済モデル」は終焉を迎え、「世界の工場」としての時代も終わりを告げました。
中国はこれまでグローバル化の最大の受益者として、外需によって国内の労働力・土地などの経済資源を動員し、経済成長を成し遂げてきました。
これは、内需に頼るだけでは不可能であり、毛沢東時代の社会主義体制では成し得なかった成果です。
さらに、米国は中国企業が西側諸国から技術を獲得することを阻止しようとしています。
そのため、米中間の貿易交渉では、知的財産の窃取、技術移転の強要、国家補助金、参入障壁などをめぐる問題が中心テーマとなっています。
バイデン政権からトランプ政権まで一貫して、技術制限と輸出規制は米中経済関係の中核に位置しています。
第三の地政学的目標は、「ルールに基づく国際経済秩序」の再構築です。
その過程において、トランプ氏はまず関税という手段を使って各国の反応を試しました。
もし相手国が建設的に米国との貿易赤字解消に協力するのであれば、関税は交渉の余地があります。
しかし、政治的な対抗意識から報復措置に出るならば、米国は容赦しません。
この試練は、各国に「どちらの陣営に立つか」を表明させるものであり、米国陣営か中国陣営かを問う「踏み絵」のような役割を果たしています。
これまでのところ、中国と歩調を合わせて米国に報復関税を課した国は一つもなく、中国は完全に孤立しています。
むしろ、ベトナムやイランのような国々が米国に接近しつつあります。
振り返ると、トランプ氏の関税戦略は最初から中国の報復を想定しており、むしろそれを誘導していたようにも見えます。
トランプ氏はまず「相互関税を課す」と表明しますが、「中国は報復してはならない」と警告します。
中国が報復に出ると、トランプ氏は最終通告を行い、撤回を要求します。
中国がそれを拒否すれば、米国は関税をさらに引き上げます。
こうして関税は、34%、84%、104%、125%、最終的には145%へと段階的に引き上げられていきました。
このプロセスは、まるでトランプ氏が穴を掘り、習近平国家主席がそこに自ら落ちていくような構図です。
この劇的な展開を世界中が目撃する中で、多くの国々は「習近平はトランプの相手にならない」との印象を持つようになり、地政学的な力関係に大きな変化が生じています。
たとえば、ロシアのプーチン大統領から見れば、これ以上、習近平氏と組むことに利がないと感じる可能性があります。
むしろ早期にトランプ氏と妥協し、ウクライナ戦争から軟着陸する道を模索する方が得策かもしれません。
戦争を長引かせて国力を消耗するより、今のうちに下りる道を探すのです。
仮にこのような展開が実現すれば、トランプ氏が大統領在任中、「関税」を通じてウクライナ戦争を間接的に解決するという、まさに「意外な形での成果」となるでしょう。
つまり、表面上は単なる貿易戦争に見える今回の一連の動きが、実はトランプ政権にとって大きな地政学的利益をもたらしているということです。
最終的に、トランプ関税は以下の複数の目標を同時に達成しようとしています。
1. 財政収入の拡大
2. 米国の再工業化の推進
3. 国際政治において、より多くの国を米国側に引き寄せる
4. 中国包囲網の形成
5. 米国主導の新しい経済秩序の再構築
中国経済の「赤いサプライチェーン」が崩壊し、中国で失業者が急増すれば台湾への圧力も弱まり、その結果、台湾から米国への投資が加速し、米国の再工業化を後押しする可能性も高まるでしょう。