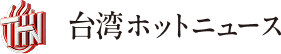台日科学技術フォーラム 開啟台日合作新時代
「インド太平洋戦略シンクタンク」(IPST)は3月28日に台北・圓山大飯店で「台日科学技術未来フォーラム」を開催しました。
半導体戦略、人工知能(AI)リスク、安全保障体制および地域協力をテーマとし、多くの著名有識者を招いて講演が行われました。
出席者には、日本の元経済産業相の甘利明氏、KDDI共同創業者の千本倖生氏、元陸上自衛隊陸上幕僚長の岩田清文氏、財信メディアグループ董事長の謝金河氏、台湾日本研究院理事長の李世暉氏らが名を連ね、科学技術と安全保障の激動する情勢の中で、台湾と日本がいかに戦略的連携を強化していくかを議論しました。

甘利明氏「日本と台湾は半導体協力を強化し、リスクのないAI世界を構築すべき」
自民党半導体戦略推進議員連盟の名誉会長も務める甘利明氏は「現在、世界はデジタルトランスフォーメーションとAIの波に直面する極めて重要な時期にあり、その中心にあるのが半導体である」と明言。
「AIチップの設計においては米国が主導的立場にあるものの、台湾企業のTSMC(台湾積体電路製造)は世界最先端の半導体製造(ファウンドリ)技術を有しており、技術と製造の両面で相互依存が生まれている」と述べました。
また、米国の労働制度では台湾企業のような効率性を実現することは難しく、特に最先端の半導体チップが単一の供給網に集中するとリスクが著しく高まると指摘しました。
こうしたリスク分散回避の必要性から、「日本は近年、半導体製造会社ラピダスを設立し、TSMCと『二重の保険』となるような協力体制を築き、安定したサプライチェーンの構築を目指している」と説明しました。
さらに甘利氏は、中国が生成系AIに必要なデータを包括的に収集している現状に対して警鐘を鳴らし、日本と台湾が連携して「リスクのないAI世界」を築き、民主的なテクノロジーの価値を共に守るべきだと強く呼びかけました。

自衛隊が統合作戦司令部を新設 岩田清文氏「台湾有事に迅速対応が可能に」
安全保障協力もまた本フォーラムの重要なテーマです。
日本の防衛省は3月24日、陸・海・空自衛隊の統合運用を目的とする「統合作戦司令部」を新設しました。
初代の統合作戦司令官には、元統合幕僚副長の南雲憲一郎氏が任命され、これまで統合幕僚長が一手に担っていた各自衛隊の統一指揮の負担を分担する体制が構築されました。
元陸上自衛隊陸上幕僚長の岩田清文氏は、この改革がもたらす二つの重要な意義を説明しました。
第一に、役割分担が明確となり、各部隊の共同行動が円滑になることで、自衛隊の作戦指揮が一層効率的になること。
第二に、統合作戦司令官が米インド太平洋軍司令部と直接連携を取ることで、日米の共同作戦の調整が確保される点です。
岩田氏は「台湾での戦争は望ましくない」としつつも、万一情勢が急変した場合には、新たな指揮体制により迅速な対応が可能となり、地域の安全保障に挑戦が生じた際にも即座に必要な措置を講じることができると強調しました。

KDDI共同創業者・千本倖生氏 「独裁国家は最終的に失敗し、日米台韓が輝く」
KDDIの共同創業者である千本倖生氏は「産業と文明の発展」という観点から講演を行い、「高度なハイテク産業が持続的に発展するためには、民主主義国家こそがその土壌となり得る」と強調しました。
千本氏は「テクノロジーの革新がAIや電気自動車産業に大きな変革をもたらしている中で、台湾は世界のハイテクサプライチェーンにおいて極めて重要な役割を果たしている」と評価。
日本企業は台湾の効率性と柔軟性から深く学ぶべきだと述べました。
また、「独裁政権は長期的に見てイノベーションの活力を維持できず、いずれ失敗する運命にある」と指摘。
台湾、日本、アメリカ、韓国といった民主主義のパートナー国家だけが、世界の先端を輝かせる新たなテクノロジーの時代を100年後まで共に切り拓くことができると力強く語りました。

謝金河氏「台日のサプライチェーン協力で中国の不当な干渉と浸透に対抗」
財信メディアグループ董事長の謝金河氏は、台湾社会における「内部リスク」の存在を指摘しました。
特に、TSMCが米国へ進出することに対して一部で悲観的な見方が広がり、世論を誤った方向に誘導していると警鐘を鳴らしました。
謝氏は、TSMCが中国企業のファーウェイ(華為)への供給を拒否し、米国企業のエヌビディア(NVIDIA)の先端チップ出荷を厳格に管理している事例を挙げ、TSMCが「技術と国防の安全保障に対して高度な責任感を持って行動している」と評価しました。
さらに、台湾と日本の間には強固なサプライチェーン協力の基盤があり、互いの信頼と技術の統合を通じて産業のレジリエンス(耐久性)を高めるだけでなく、中国からの不当な干渉や情報浸透工作への対抗力を強化し、民主主義陣営の経済的自立を維持するうえでも重要な意義があると強調しました。
-768x432.jpg)
台湾日本研究院理事長の李世暉氏は、世界は現在「チェーンパワー」を中核とする新たな国際戦略秩序へと移行しており、台湾と日本はその重要な交差点に位置していると指摘しました。
李氏は、「チェーンパワー」とは三つの連携から構成されていると説明。
中国が軍事的ラインとする第一列島線(九州沖から沖縄、台湾、フィリピンを結び南シナ海に至るライン)に位置して安全保障を担う「アイランドチェーン」、半導体とAI技術を供給する「ハイテクサプライチェーン」、そして民主主義の価値観を共有する「民主主義チェーン」を挙げ、「東アジアの将来はこの三つのチェーンによって大きく左右される」と強調しました。
李氏はまた、賴清德総統が昨年の就任演説で述べた「三つの連携」と「五つの信頼産業」が、自身の提唱する「チェーンパワー」の概念と高度に一致しているとも述べました。
「五つの信頼産業」とは半導体、AI、防衛産業、セキュリティ管理、次世代通信を指し、台湾の戦略的自立を維持するための中核的な支柱であると述べました。
さらに李氏は、トランプ政権が1980年代のアメリカの主要産業を再興しようとしている政策や、米中対立に起因する技術規格の競争などが、台湾と日本を地政学的に強く結びつけていると述べました。
たとえば、TSMCの日本およびアメリカへの投資の優先順位は、二国間の半導体協力の深さと方向性に直接影響を与えると分析しています。
李氏は、台湾と日本がより一層協力し、サプライチェーンの再構築や技術秩序の再編といった課題に共同で対応していくべきだと呼びかけました。