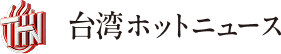台日経済動向と発展の機会

皆様こんにちは。
私は先ほどの岩田先生の講演に非常に感銘を受けました。
彼を見たとき、私は根本博将軍が1949年の古寧頭戦役で台湾にもたらした貢献を思い出しました(根本博は元日本陸軍中将。台湾の国民党政権を助けるため日本を密出国して金門島の古寧頭戦役に参加し、中国人民解放軍の撃破に貢献した)。岩田先生は戦争の重要な場面で半導体の役割について話してくださいました。
台湾積体電路製造(TSMC)がアメリカに1000億ドル(約15兆円)を追加投資することについて、最も気にしているのは誰か。
もちろん中国です。
台湾には多くの中国の協力者がいて、さまざまな形でTSMCをおとしめる発言をしています。
国民党の馬英九・元総統は「賴清徳総統が台湾を売り渡し、重要な技術をすべてアメリカに売った」と批判しています。台湾にいる多くの中国協力者がバッシングしています。
TSMCはなぜアメリカに進出するのでしょうか?
岩田先生がおっしゃった通り、将来の防衛においてTSMCは非常に重要な役割があるため、アメリカはもっと厳重に管理しなければならないのでしょう。
ご存じのように、中国企業のファーウェイ(華為)のチップをアメリカが調査した結果、TSMCのチップがいっぱい入っていました。
中国はシンガポールやベトナムを経由して、NVIDIAのH100(生成AI向けGPU)チップも約5万個手に入れたそうです。
中国はそのチップで生成AI「DeepSeek(ディープシーク)」を梁文鋒氏(ディープシーク創業者)と共にを構築したのです。
これによって、半導体はいかに安全保障と密接に関連していることがわかります。
半導体は国防です。岩田先生のおっしゃった通り、日台関係の基本は安倍元首相が述べた「台湾有事は日本有事」です。
私はそこで「台湾は必ずしも有事が起きるかわからないが、日本は必ず有事になる」と言いたい。この意味はわかるでしょうか。
台湾と中国には深い恨みはありません。唯一の争いは、台湾の主権に関する争いです。
中国は「台湾は中国の不可分の領土」と言っていますが、台湾は受け入れていません。
しかし、日本と中国の間には抗日戦争の時代の深い恨みがあります。
一方で、台湾人が日本に行くのをどれだけ好むかを知っておいてください。
私たちが日本でタクシーに乗ると、運転手は「どこから来たのですか?」と尋ね、「台湾人です」と答えると、まるで兄弟のように接してくれます。
これが台湾と日本の絆の基盤です。
1980年代から現在までを振り返って考えてみましょう。
台湾の経済は日本と完全に結びついています。私が1984年に財訊に入ったとき、上司は邱永漢氏(台湾出身で日本を拠点にして「金もうけの神様」と言われた実業家)でした。
彼は毎回日本から帰国する際、私を食事に呼んでくれました。
彼は「現在、日本でどんな産業が成長しているかを注目すれば、2年後には台湾でも同じことが起きるだろう」と話していました。
日本の発展を把握すれば、台湾の経済発展の方向を簡単に理解できました。
1980年代は円も台湾元も対ドルレートで上昇を始めました。これにより株式市場や不動産が急騰しました。
バブル時代の日本を思い出すと、私は銀座で食事を終えた後にタクシーを呼ぼうとしましたが、1万円札を手にしていないとタクシーを捕まえることができない時代でした。
その時期は台湾でも「お金があふれて溺れるほど」と言われましたが、お金が膝からへそ、さらに鼻の穴に達するくらいの状況で、日本と台湾の株価は暴落しました。
1989年に日本のバブル経済が崩壊した後、日本は長い調整期に入ります。
中国はでは1978年から改革開放政策が始まり、1990年代には「世界の工場」と言われ、中国経済は大きく成長していきます。
日本と台湾は同時に「失われた30年」に突入しましたが、いま台湾の経済が日本より強く見える理由は何でしょうか? それはまず、台湾が人工知能(AI)と密接に結びついていることです。
次に、台湾が世界で最も重要な半導体供給国になり、TSMCが台湾の重要な神経中枢、いわゆる「護国神山(台湾の中央山脈の異名)」となったからです。
このため、台湾は持続的に前進できています。これは30年間の中に非常に重要な転換点です。
さらに皆さんに注目していただきたいのは、台湾企業が中国にいち早く進出し、利益を得ていたことです。
しかし中国の状況が悪化し始めたとき、台湾企業は最も早く中国から撤退しました。対照的に日本は今でも多くの企業が中国市場を忘れられずにいます。
したがって日本経済は台湾に比べて転換が遅れていると言えるでしょう。このことが台湾と日本の経済構造の大きな違いです。
振り返ると、日本の最も厳しい時期はおそらく2011年の東日本大震災の時でした。
安倍晋三氏は2012年に首相の座に返り咲き、最も長く在任する首相となりました。彼が行った重要なことは、量的緩和の金融政策に取り組んだことです。
また、日本の観光産業を積極的に発展させ、世界中から観光客が日本に訪れるようになりました。
安倍氏の経済政策「三本の矢」は非常に重要でした。
第一の矢は、大規模な量的緩和による金融政策です。第二の矢は国家の財政支出を拡大し、柔軟な財政政策を採用したことです。
第三の矢は、構造的な経済改革を推進し、民間の投資を促すことです。
バブル崩壊後の30年間で、日本では多くの不動産会社や銀行が破綻し、消費が減少しました。
デフレが深刻となり、安倍政権がインフレターゲットを2%に設定しました。この2%は現在ようやく実現されてきています。
一方で安倍氏は過度な円高を是正し、消費税を引き上げ、さらに日本銀行による公開市場操作を行いました。
公共事業の国債を購入し、長期的に保有する無制限の金融緩和政策を実施しました。
円安は日本のデフレを解消するために最も重要な戦略でした。
ここ数年、円はだいたい1ドル=150円前後に推移しているので、世界中の多くの人々が日本に観光に行くことを楽しんでいます。
日本では何を食べても美味しくないものには出会わない。そして全国どこへ行っても比較的安全です。これが日本の観光産業を再生させています。
安倍氏は生前、日本に訪れる観光客を4000万人にする目標を掲げていました。
コロナの影響を受けた後、昨年の日本への観光客は3686万人に達しました。日本は観光大国に変貌しました。
この中で韓国が第1位、中国が698万人で第2位、台湾が604万人です。
人口比率では、台湾は日本を訪れる観光客が最も多い国です。人口は2300万人で、観光客は600万人を超えているのです。
驚くことに、604万人のうち19%が1年の間に日本を10回以上訪れています。ある人は自宅の台所に行くように1か月に1回日本を訪れ、美味しい料理を楽しんでいるのです。
私は台湾の中で日本経済が良くなると最初に公言した人間です。
2017年に「日本経済は徐々に良くなり、台湾も継続的に良くなる」と言いました。当時は誰も信じませんでした。
日本のことを低く見積もっていたからです。しかし2020年になり、アメリカの著名投資家ウォーレン・バフェット氏が日本の5大商社である三井物産、三菱商事、丸紅、住友商事、伊藤忠商事の株を購入し始めました。
コロナ禍で日本の商社の5%の株式を買い、今に至るまで売却しておらず、さらに追加購入をしています。
バフェット氏は「日本の商社はアメリカと比較しても株主に非常に優しい」と言っています。
日本の5大商社は新株を発行せず、株主の権益が希薄化されないのも大きなポイントです。
さらに、株主には非常に魅力的な価格で自社株を買い戻すことを提供しています。
バフェット氏の投資は世界中の注目を集め、多くの機関投資家が日本への大規模な投資を開始しました。
バフェット氏は2022年3月にTSMCの株も購入しましたが、その後すぐに売却しています。戦争を恐れていたからです。しかし日本の5大商社の株を売ることはありません。
このことから日本に対する投資家の信頼感の高まりがうかがえます。
日本ではより積極的かつ前向きな改革が始まっています。
東京証券取引所は日本の上場企業に対し、株価純資産比率が1未満の企業には定期的に改善報告を提出させています。
1年以内に改善が見られず、株価純資産比率が1を下回った場合、上場は廃止されます。
かつて日本の上場企業の経営者は非常に消極的で保守的でした。
そのため企業は株価をあまり重要視していませんでした。しかし「改善しなければ、上場廃止」となり、大和証券や三菱UFJ銀行などの株価は急上昇しました。
日本の銀行は以前、全世界の銀行ランキングで30位以下にまで落ち込んでいましたが、三菱UFJ銀行は世界第7位の銀行となり、日本は再び競争において有利な位置に戻りつつあります。
この30年の間、特に最近の2年間で日本には急成長している産業があります。
岩田先生が言及したように、日本は将来に向けて非常に強力な防衛産業を形成し始めています。
防衛産業を代表する三菱重工、川崎重工、石川島播磨工業(IHI)の株価は上昇しています。
現在、世界中の軍需産業が大きく成長しており、株価も大幅に上昇しています。
ドイツのラインメタル社はロシア・ウクライナ戦争の影響で20倍にまで上昇しました。ただ世界で唯一、台湾の株価だけが上昇していません。
なぜなら最近の政治的な要因、特に「青白連合」が防衛予算を削減しているからです(シンボルカラーが青色の国民党と白色の民衆党の2野党が立法院=国会で多数派を占めており、与党民進党の予算案に反対している)。
自動車業界は注意が必要です。
中国の電気自動車(EV)が旋風を起こし、さらにトランプ政権が自動車に関税をかけることになり、日本にとって大きなプレッシャーとなります。
日本で生き残るのはトヨタ自動車だけかもしれません。トヨタはハイブリッド車で良好な業績を維持し、将来は水素燃料車で重要な役割を果たすことが期待されています。
日本の多くの産業が中国との競争に直面しています。
日本はかつて自動化設備の分野でリードし、最近は産業用ロボットや協働ロボットの分野で強みを持っています。
しかし今、中国が型ロボットの分野で急成長しており、AIの発展と高度に結びついています。
台湾と日本が今後の発展においてより緊密に結びつくことがますます重要になっています。
失われた30年を経て、日本経済はバブル崩壊の痛みから回復し、徐々に正常な経済状態に戻り、競争力を回復しています。
昨年の8月5日に日本はゼロ金利を終了し、基本金利を0.25%に設定しました。10年国債も1.0%になりました。
日本は徐々に健康的な道を歩み始めています。
中国の10年国債利回りはかつて8%を超えていましたが、今では2%台にまで下がっています。
一方で日本はかつての低利率から戻りつつあり、30年国債利回りも初めて中国の国債利回りと交差しました。
日本はバブル経済の辛苦を乗り越え、そのバトンを中国に渡そうとしています。
現在、TSMCが熊本に工場を設立しています。
私は台湾と日本の協力がより強固なサプライチェーンを築くと信じています。
今後、台湾と日本は技術と人材を補完し合い、より大きな効果を生み出すはずです。
半導体の協力を深めていくことが重要です。
熊本はTSMCによって発展し、TSMCも日本での成長を通じてより広い発展の道を見いだせると考えています。
私の報告はここで締めくくらせていただきます。